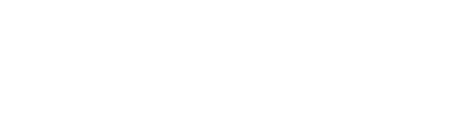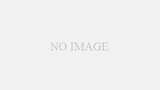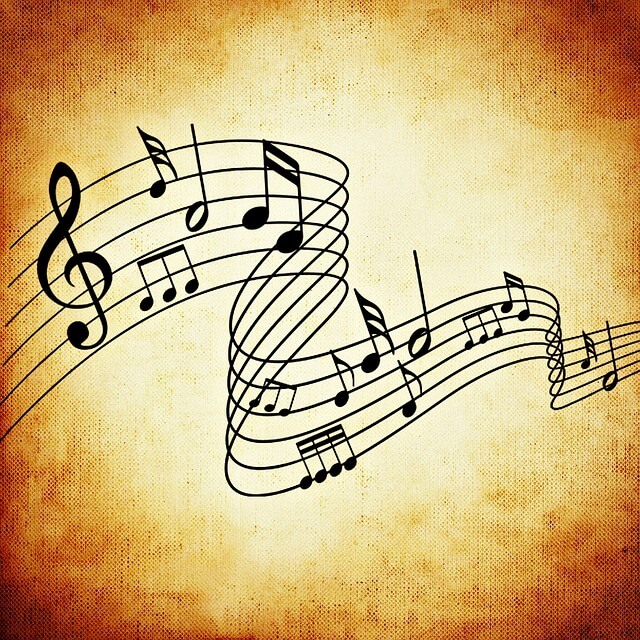
曲の流れとリズム
今回はケルト系伝統音楽を構成する曲の流れやリズムの事について。
曲
伝統音楽には、1分以内で終わるような曲もあるし5分を超えるような曲もあります。
1曲として作る時は、複数の曲をつなげて1曲にするのが伝統音楽の基本的な構造です。
長さにもより前後しますが、大体の曲が2個か3個つなげられています。
そして、そのつなげられた物を「set(セット)」と呼びます。
演奏の流れ
多くの伝統音楽は同じ曲を何度も繰り返すスタイルで進行していきます。
前半の8小節を2回、後半の8小節を2回、合計32小節、これで一曲にですね。
※基本32小節だがそれ以外も存在している。
演奏するときは、例えば1曲を3回演奏したら次の曲に変わり、次の曲をまた3回弾いたらさらに次の曲へ、といった感じで延々続きます。
いつ終了させるかなどのルールは決まってないので、満足したら終わりです。
比較的多いのは1曲を2回か3回のようですが、別に決まりは無いです。
曲が切り替わる瞬間は、聴いててテンション上がるポイントですね。
セッションなどでは曲の順番が決めてあったり、参加者で順番に出し合ったり色々です。
でも特にこの流れじゃないとダメだとかはないので、セッションごとのルールに従いましょう。
ただリズムだけは別で、基本的に同じリズムの曲を連続で演奏していきます。勝手に速くしたり遅くしたりしてはいけません。
多人数でセッションするときは最初に主催者に尋ねてルールを確認して、周りに合わせて空気を読みながらいい感じにやろう!その場のノリに合わせて楽しめ!
でもマナー&ルールはしっかり守ってね!
セッションについてはまたいずれ。
様々なリズム
伝統音楽には様々なリズムがあり、それぞれ名前があります。
リールやジグ、ポルカなど聞いた事ないですかね?
また個別に書いていきたいと思いますが、とりあえず列挙します。
- ジグ(jig)
- ダブル・ジグ(double jig)
- スリップ・ジグ(slip jig)
- シングル・ジグ(single jig)またはスライド(slide)
- リール(reel)
- ポルカ(polka)
- ホーンパイプ(hornpipe)
- フリング(fling)
- マズルカ(mazurka)
- ワルツ(waltz)
- ストラスペイ(strathspey)
- セット・ダンス(setdance)
- バーン・ダンス(barndance)
- ジャーマン(german)
- エアー(air)
などなどたくさんあります。
他にもあるみたいですが浅学の為、分かる範囲ではこれだけかな?
リズムも個別に調べて書いて行くので、今後調べて追加していきます。
最後に
というわけで、曲の流れについてはこんな感じです。
リズムごとに特徴があって面白いので、みんなも演奏すればいいんじゃないかな!
広がれ……伝統音楽の輪……!